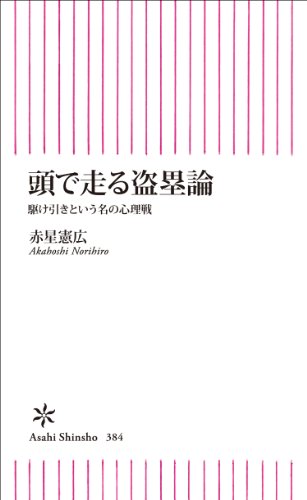★★★☆☆
あらすじ
同じ特殊学級に子供を通わせる元原発の技術者の男に、自分と息子に起きた出来事をゴーストライターとして物語るよう頼まれた作家の男。
感想
知的障害のある子供を持つ父親が主人公だ。ある時、主人公が20歳若返り、子供が20年歳を取る不思議な現象が起き、親子の立場が「転換」してしまう。主人公はその現象が起きた意味を考えながら、市民運動に巻き込まれていく。
人に何かを教えている時、逆に相手から教えられているような気がすることがあるように、親子の関係においても親である自分が子供のように感じてしまう瞬間があるのだろう。それを具現化したような物語だ。宇宙的な意思を預言されているらしい息子に従い、主人公は動く。
学生運動や市民運動、原発や天皇に関する議論、さらに右翼のフィクサーが登場する物語だ。主人公が息子の代弁者として荒ぶる学生たちの前で大演説をするシーンがあり、正直なところちょっとしんどく感じてしまったのだが、この当時の人たちはこれをリアリティの感じられるものとして興味深く読んだのだろうか。この頃はまだ戦争経験者がたくさんいたので、世界の核の脅威などがより真実味のあるものとして感じられたのかもしれない。皆真剣に世界について考えている。
そして現在はこの時と大して変わっていないどころか、むしろ核保有国は増えているわけだが、人々は運動を拡大するどころか気にしなくなって何食わぬ顔で生きている。不思議に感じてしまうが、要は単純に慣れてしまったのだろう。「近い将来、ほぼ確実にこの地を大地震が襲います」と言われても、特に何をするわけでもなくただ漫然と日々を過ごしているのと同じだ。人間は爆発するまで爆弾の傍で平気で火遊びが出来てしまう生きものだ。想像力があるようで案外と、ない。
自分の子供にしかできないことがきっとあるはずだ、そのために生まれてきたと思いたい親の気持ちが強く感じられる物語だった。それは一から十まですべてをたった一人で成し遂げるようなものではなく、試合の途中で誰かに代わって突如現れるピンチランナー的な存在としてでもいい。失敗の恐れを抱きながらも気持ちは昂る。そんな気持ちが味わえる人生であってほしい。
ある親子の出来事をゴーストライターとして物語る私、というこの小説の形式自体にもそんな気持ちが表れているような気がした。
著者
大江健三郎
登場する作品
この作品が登場する作品